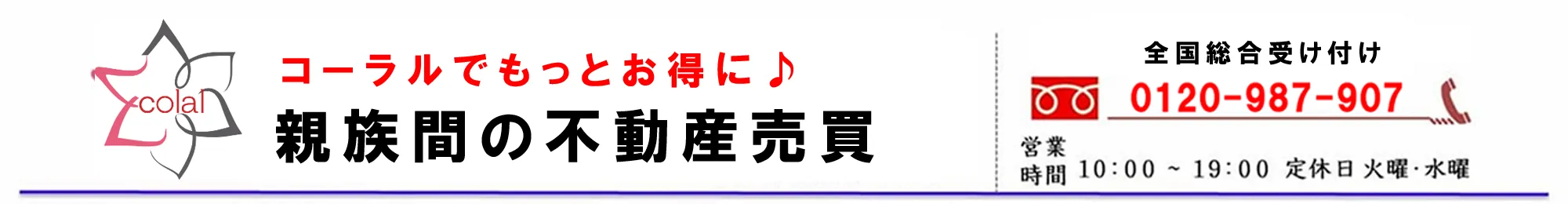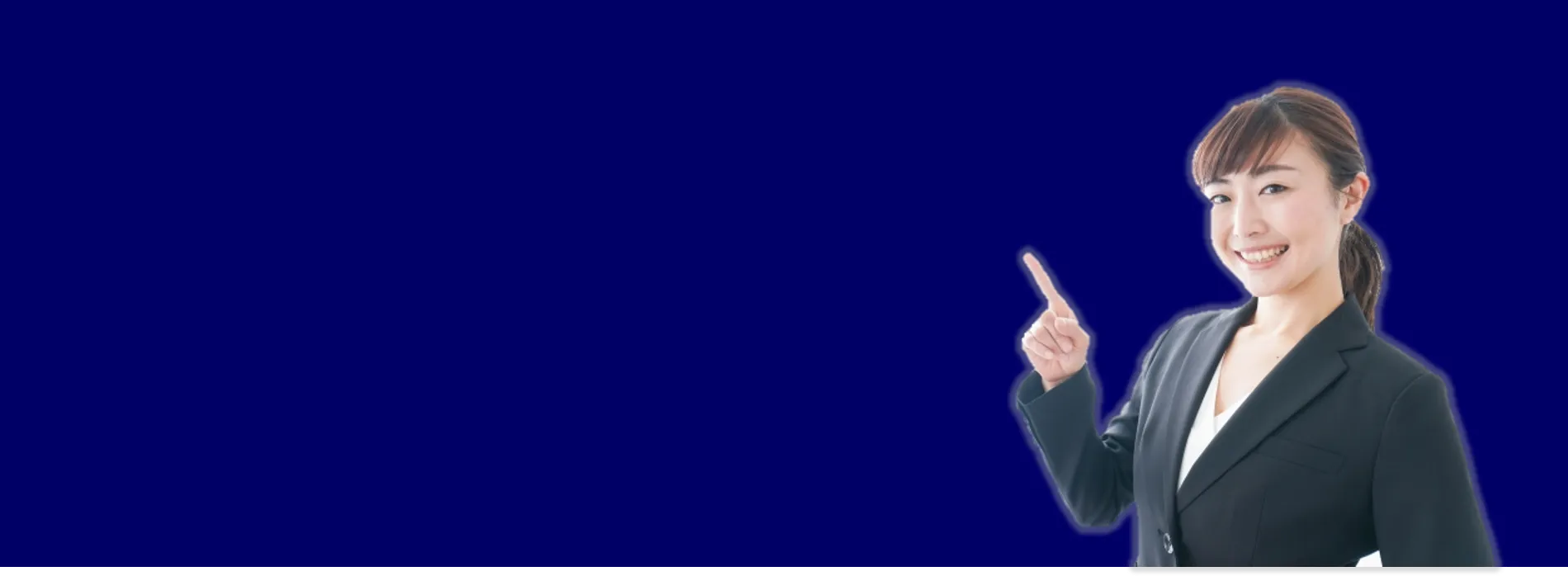親族間売買の流れについて、具体的な手順やスケジュールを詳しく解説します。
親族同士で不動産を売買する場合、一般の取引とは異なる独特の流れがあります。そのため、しっかりとした理解を持って行動することが大切です。
まず、売主と買主の間で意思確認を行います。お互いの意向や価格について話し合い、売買の合意を形成します。ここでのコミュニケーションは、トラブルを未然に防ぐためにとても重要です。
次に、具体的な売買契約について検討します。契約書には物件の詳細や売買価格、引渡し日などの重要な情報を記載します。この契約書をお互いに確認し合うことが、スムーズな取引実現につながるでしょう。
その後、必要な手続きを進めます。具体的には、登記に関する手続きや引渡しに必要な書類を準備することです。これらの手続きは専門的な知識が求められるため、必要ならば専門家の助けを借りることをおすすめします。また、親族間だからこそ生じやすい感情的な部分にも配慮しながら進めると、良好な関係を保つことができるでしょう。
最後に、すべての手続きが完了すれば、物件の引渡しとなります。この流れを理解していれば、親族間でもスムーズに売買を進めることができるでしょう。
親族間売買とは何か、流れの中でのメリットとリスクとは?
親族間売買とは、家族や親しい親族同士で不動産を売買することを指します。
関係記事 ☞ 親族間の不動産売買とは⁉
この取引は、一般的な不動産取引の流れや手順とは異なり、相手が信頼できる身内であるため、心の距離が近い点が特徴で価格や条件の交渉が比較的スムーズに進むことが多いです。
しかし、信頼関係がある一方で、感情が絡むことが多いため、時としてスケジュールや手順が後先ばらばらとなり収集がつかなくなったり、金銭的な面や法律的な手続きに関しても考慮せず進めたため思わぬ障害が出てきて進み具合が悪くなったりといったトラブルが発生しますので注意が必要となります。ゆえにトラブルを防ぐためには専門家を入れ事前に話し合いをしっかり行うことが大切になります。
例えば、手順でのトラブルでありがちな事を見てみましょう。
① 売買代金の受け渡しを売買契約書で約定せず適当に決めてしまったため、いつまでたっても売買完了しなかった。
② 土地面積を口約束で決めたため、後に対象面積相違により大きなトラブルになり、いつまでたっても決済できなかった。
③ 売買価格を親族間という事もあり適正価格よりも安価な価格で売買して、税務署からみなし贈与があったとされ、その負担をどうるるかで親族間で揉めた。
などなどあるのです。
こういうことを避けるためにも、親族間売買では契約書作成は不可欠です。仮に後々トラブルが発生した場合、自分の主張を裏付けられる証拠となりますので、必要な情報は明確にしっかりと記載しなければいけません。このように、親族間売買には特有の利点とリスクが伴うため、しっかりした計画と準備が求められるのです。
親族間売買の一般的な流れ、手順
ここでは、親族間で不動産売買するときの一般的な、具体的な流れを解説します。
一般的に親族間の不動産売買時は、①確認と計画(価格や条件を決める)、②必要書類の準備、③売買契約締結、④決済・引き渡し、⑤登記申請、⑥税務申告」という手順で進めます。
売買するに当たって、まずすべきこととは
一般の不動産売買と比べて若干異なる点があります。
一番初めに行うべきは、売買の意向を確認することです。売主と買主の間でしっかりと話し合い、条件を整理します。不動産の価格や引き渡し時期についてもお互いに合意することが重要です。この段階でのコミュニケーションが、その後のトラブルを防ぐカギとなります。
ステップ1: 売買契約内容の確認、計画
ステップ1では、売買契約内容の確認が重要なプロセスとなります。
この段階では、売主と買主双方が合意した内容をしっかりと確認し、契約書に記載する必要があります。まずは、物件の基本情報の整理から始めます。物件の所在地や種類、面積、築年数などの詳細を確認し、誤解が生じないように注意を払いましょう。これらの情報は、後のトラブルを防ぐために確実に記載する必要があります。
次に、売買価格や代金の支払い方法についての確認です。親族間での売買でも、価格設定は公平で透明性がある適正価格である事が求められます。お互いが納得できる価格を設定し、支払いのタイミングも明確に定めましょう。支払い方法には、現金での一括払い、銀行振込、またはローンを利用するなど、さまざまな選択肢がありますので、慎重に検討して決めると良いです。
また、引渡しの時期や条件も重要なポイントです。物件の引渡しが行われる日と、どのような条件で引渡しが行われるのかを明確にしておくことが大切です。例えば、物件の現状や引越しにかかる時間、さらに、必要な書類の準備についても話し合う必要があります。親族間であるとはいえ、きちんとした契約がないと、後々のトラブルを招くこともあるため、慎重なる行動が求められます。これらの点を確認し合えば、売買契約の進行がスムーズになります。
住宅ローン利用は時間配分も考慮しよう
売買代金に住宅ローンを利用するときは、ローン申し込み&事前審査から本審査、住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)締結、融資実行まで時間のかかる場面が多々ありますので、時間配分には十分注意を払いましょう。
ステップ2: 必要な書類の準備
ステップ2では、親族間売買において必要な書類の準備が重要な位置を占めます。
書類は法律的な手続きの基盤となるため、漏れがないよう慎重に進める必要があります。まず、基本的な書類として「売買契約書」が挙げられます。この契約書には、物件の詳細、売買価格、引渡し日などが明記されていることが重要です。お互いの確認をしっかり行い、サインをする際は双方に保管用のコピーを残すと良いでしょう。
次に、所有権を証明する「事項説明書(登記簿謄本)」が必要です。登記簿は、物件の所有者や負担状況を示す公的な記録です。この書類に基づき、売主が本当にその物件の所有者であることを確認します。また、所有権移転登記を行うためにも必要となりますので、事前に取得しておくことをお勧めします。
さらに、物件の評価を確認するための「不動産査定書」か「不動産鑑定書」も重要です。親族間であっても、適正価格での売買が求められます。これら書類によって、実際の市場価値が明らかになるため、トラブルを防ぐ助けにもなります。
最後に、税金や費用に関する書類も忘れてはいけません。譲渡所得税や仲介手数料などの説明を受け、自身の負担を把握することが大切です。全体を通じて、必要な書類をしっかり準備し、スムーズな取引へとつなげていきましょう。
ステップ3: 売買契約の締結
ステップ3は、売買契約の締結です。
親族間であっても、売買契約は非常に重要なステップであり、慎重に進める必要があります。この契約書は、物件の詳細、売買価格、引渡しの条件などを明確に記録するための文書です。
まず、契約書には物件の正確な情報を記載します。具体的には、物件の住所、土地・建物の面積、種類などが含まれます。この部分を正確に記載することで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
次に、売買価格や支払い方法を明記します。親族間では、金額設定が難しい場合もありますので、事前に話し合いを重ねておくと良いでしょう。また、支払い方法についても現金一括か分割払いか、明確に記載しておくことが重要です。
さらに、契約締結日や引渡し日などの重要な日程も取り決めておきます。これらの日程は、両者が合意した上で、契約書に記載しておくとスムーズな進行に繋がります。
最後に、契約書は双方の署名と捺印を行うことで、法律的に有効となります。この契約書は大事な記録として保管しておく必要がありますので、紛失しないように注意しましょう。親族間の売買であっても、契約書の重要性を理解し、丁寧に進めることで、安心して取引を行うことができるでしょう。
ステップ4: 決済(売買代金の支払い)・引き渡し
ステップ4: 売買代金の支払いは、不動産取引において重要なプロセスです。
この段階では、事前に取り決めた売買価格を送金または現金で支払うことになります。
親族間での売買は、一般的な不動産取引よりもフレンドリーな雰囲気で進むことが多いですが、金銭のやり取りは慎重に行う必要があります。トラブルを避けるために、支払い方法を明確にし、どの時点でどのように支払うのかをあらかじめ確認しておくことが大切です。
たとえば、売買契約を交わしたときに手付金を支払う場合、それが将来の代金に充当されることを確認しておきます。また、残金の支払いを行う際は、振込明細書や受領書など、支払いを証明するための書類をしっかりと保管しておくと安心です。
売買代金の支払いは、買主と売主の信頼関係を強化する機会でもあります。事前に金銭面の合意事項を共有し、理解し合った上で取引を進めることで、トラブルを未然に防ぎ、互いの信頼関係を築くことができます。
このステップが無事に完了すれば、次のステップ、つまり物件の引渡しへと進んでいくことができます。親族間の売買においても、冷静に正確な手続きを進めることが大切です。
ステップ5: 登記申請の手続き
登記申請の手続きは、親族間での不動産売買において非常に重要なステップです。
この手続きによって、所有権が正式に移転し、法律的にもその取引が認められます。まず初めに、必要な書類を確認しましょう。一般的に必要とされる書類には、売買契約書、登記申請書、印鑑証明書、住民票、固定資産税納税通知書などがあります。これらは必ず用意する必要がありますので、不足がないか事前にチェックしてください。
次に、登記申請書の作成に取り掛かります。登記申請書には、物件の情報や売主・買主の情報などを正確に記入する必要があります。書類の不備があると、申請が受理されないこともありますので、慎重に作業を進めましょう。作成した申請書と必要書類をすべて揃えたら、法務局に提出します。
提出後、法務局での審査が行われ、問題がなければ登記が完了します。これにより、所有権が正式に移転し、あなたの名義として登記されることになります。登記が終わることで、第三者に対しても権利を主張することができるようになりますので、この手続きは非常に重要です。
最後に、登記完了後は、登記簿謄本を取得することをお勧めします。これにより、正式な証明書が得られ、今後の取引などに役立てることができます。親族間売買であっても、法的手続きを怠ることはできませんので、しっかりと進めましょう。
ステップ6: 税務申告と納税
親族間売買が完了した後、次に考慮すべきは税務申告と納税の手続きです。
不動産売買にはさまざまな税金が関わってくるため、これを怠ると後々トラブルが生じる可能性があります。特に、親族間での取引は特別な配慮が必要となるため、注意が必要です。
まず、売主(親族)が不動産を売却した場合、譲渡所得税が発生する可能性があります。この税は売却価格から取得費用を引いた金額に課税されます。売却によって利益を得た場合には、必ずこの申告を行い、納税をする義務があります。税務署に適切な書類を提出し、正しい税額を計算して納付することが求められます。
また、買主にとっても不動産取得税がかかります。これは、物件を取得した際に一度だけ支払いが求められる税金です。物件の評価額に基づいて計算されますので、正確な情報をもとに申告を行う必要があります。
さらに、親族間での取引の場合、特別控除が適用される場合もあります。例えば、一定の条件を満たす場合には、譲渡所得税や不動産取得税に優遇措置が取られることがありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
最後に、税務申告は一般的に年度の終わりに行いますが、具体的な期限や方法は地域によって異なることがあるため、早めに確認しておくことが重要です。正確な情報を得るためには、税務署や税理士に相談することをおすすめします。適切な対応を行うことで、安心して取引を終えることができるでしょう。
コーラルでの親族間売買取り組み時の手順&流れ、スケジュール
ケース1 買い手が住宅ローンを利用する場合
ここでは、コーラルへ売買仲介をご依頼いただいた場合の手順やスケジュールを解説します。住宅ローンを利用するケースの手順解説ですが、住宅ローンを利用しない場合はステップ4、ステップ6の手順が無い事となります。
●お取引の流れ

まずは『無料通話』または『お問い合わせフォーム』よりご相談下さい。

お客様よりお問い合わせ頂きましたら、親族間売買の取引に長けた担当スタッフよりご返答申し上げます。
担当より今回の取引概要をヒアリングさせて頂き、ベストな解決方法のご提案、及び今回の取引に伴う諸費用をご提示させて頂きます。
売主様、買主様ご納得いくまでご相談頂き、弊社へ受任されるかどうかをご判断ください。
ここまでは無料でご対応可能です。

金融機関へ住宅ローン借入審査を打診する為に物件資料の取得及び物件資料の作成を行います。
その費用として(33,000円)をお客様より頂きます。
着金確認が完了でき次第、各金融機関へ打診。
既に金融機関の目星がついている場合には、事前審査、本審査の打診手続きを行います。
費用:33,000円(税込)

弊社にて住宅ローンの審査受付可能な金融機関をお探しし、ご紹介させて頂きます。
お客様個人資料をご準備頂き、事前審査お申込み手続きを行います。
お客様資料は下記資料をご用意ください。
・源泉または確定申告書
・顔写真付き身分証明書
・勤続年数の確認ができる使用(例:保険証)
・借入がある場合、返済予定表
・その他、必要に応じて御用意していただきます。

買主様の住宅ローン審査が終了次第、売買契約の締結を行います。
費用内訳
・手付金 (必要に応じて)
・収入印紙 (売買代金に応じて変動)
・資料取得費(必要に応じて)
・仲介手数料
(売主様、買主様それぞれ、契約時の仲介手数料として仲介手数料の半金をご契約時にお支払い頂きます。)

売買契約締結が終了次第、住宅ローンの本審査を行います。
本審査に必要お客様資料のご準備をお願いします。
承認が下り次第、所有権移転日(決済日)を確定し、金融機関との間で金銭消費貸借契約書をご契約頂きます。
費用
・収入印紙(電子契約の場合、不要)

当日は、司法書士へ登記手続きに必要な書類(権利証や印鑑証明書)を渡していただき、登記手続きができる準備が整い次第、住宅ローンの借り入れが実行されます。
買主様から売主様へ売買代金の支払い等を行い、無事に売買手続きが完了次第、司法書士が管轄法務局へ登記申請を行います。
費用内訳
・売買代金 (取引金額に応じて)
・収入印紙 (売買代金に応じて変動)
・登記費用 (必要に応じて)※1
・住宅ローン借入費用(借入金額によって変動)
・仲介手数料(残りの半金のお支払い)
※1 登記費用は別途必ずかかります。またその他実費(書類取得費用や現地までの交通費など)については別途かかる場合があります。

決済日から大よそ1ヵ月くらいで法務局より登記完了書類が司法書士宛に送られてきます。
それらを売主様と買主様へご郵送し今回のが完了となります。
以上、コーラルで仲介させていただいたときの親族間の不動産売買時の手順を解説しました。
おおよそ上記手順に従い進めていますが、時としてこの手順で進められない場合もあります。例えば親族間で不動産売買する事は決めたが、しかし、対象不動産の適正価格を決めていないので、相手と交渉してほしいというものがあります。コーラルは不動産会社なので売買相手と売買価格の調整は努力したしますが、しかし、交渉はできません。交渉できるのは弁護士だけですので不動産会社にはできないのです。また、離婚する夫婦間のマイホーム売買も親族間売買の範疇となりますが、この場合の夫婦間の離婚事案調整も、例えば離婚時期の調整や養育費問題調整などもできません。これまた弁護士だけができる業務なのです。
親族間の不動産売買は、親族間で不動産を売買する事から来る特殊な空気が流れるものです。ゆえにスケジュールがとても簡潔に済む場合もあれば、1年以上になるケースもあります。
親族間で売買するからと軽く考えず、進めるときはコーラルなどの親族間売買にたける不動産会社に事前相談されることをお勧めいたします。
親族間売買のスケジュールで失敗した事例紹介
親族間売買で起こった失敗事例を紹介します。この事例はスケジュール管理を甘く見て進めた事で起こった事例になります。
以下のような実際に親族の間で不動産を売買したケースで、スケジュール管理を甘く見て失敗し、終には売買そのものをあきらめ負えなくなった事例は数多く存在します。ゆえに親族間売買を親族間だから簡単だと甘く見ず、しっかり手順や流れを理解するべきです。
ケース1 売買締結前の準備不足
親族間売買は具体的な手順前から始まっています。これを怠ると後々親族間の関係がごたごたになることがあります。
売買締結前の準備不足について考えてみましょう。親族間の不動産売買において、売買をスムーズに進めるためには、契約締結前に十分な確認と準備を行うことが非常に重要です。しかし、実際にはこの確認と準備が不足しているケースが少なくありません。たとえば、親が子に不動産を譲る際に、物件を適切に査定しないで売買価格を決めていたり、買い手の支払い能力を過信していたりすることが見受けられます。
このような準備不足がもたらす問題には、後でトラブルが発生するリスクが高まることが挙げられます。例えば親子間だからといって価格設定を曖昧にしてしまうと、みなし贈与税がかかったりと、売買後に問題を引き起こす要因となります。また他の親族が「なぜあの価格なのか」と疑問を持ち、不公平感が生じることも考えられます。
買い手の支払い能力の過信によるトラブルはしっかり事前確認していれば避けれるケースですが、親族間という間柄からか、しっかり確認せず売買へ進むケースがあります。支払い能力不足では期待していた住宅ローンが借りられず、売買が進まず途中でストップしてしまうケースもあります。このような状況を避けるためにも、売買締結前の準備は欠かせません。
最終的に、親族間であっても、専門家の助けを借りて準備を怠らず、確実な手続きを進めることが、後々のトラブルを回避するためのキーポイントとなります。
ケース2 親子間売買代金の支払い管理で失敗
分割支払いの問題について、親族間の不動産売買では時々見られるトラブルの一つです。具体的なケースとして、親が子に対して家を売却し、購入代金を分割で支払うことにしたとします。この場合、一見、親子間の信頼があるため、問題が起こることはないように思えます。しかし、実際にはそうした単純な関係が裏目に出ることがあります。
まず、契約書に分割支払いの具体的な条件を記載していない場合、後々にトラブルに発展する可能性が高まります。例えば、購入者側が金銭的な事情により支払いが遅れることがあった場合、売却側はどのように対応すればよいのかが不明確となります。同じ親族だからこそ、感情的な部分が絡むことが多く、トラブルは避けがたいのです。
また、分割払いの際には金利の設定や支払い期限についても、事前に合意を形成しておく必要があります。親子間の関係により、相手を気遣うあまりに条件を曖昧にしてしまうことが、将来的な問題を引き起こす原因になります。
ケース3 夫婦間売買の手順管理で大失敗
離婚を考える際、売り手の住宅ローン残債返済法や買い手の住宅ローン借り入れ法についても十分な検討が必要です。
たとえば、離婚時に一方の配偶者が家に住み続け、もう一方がローンを支払うという状況が発生すると、経済的な負担が不公平に感じられることがあります。この場合、借入名義や契約条件によって思わぬトラブルが起きることがあります。
さらに、売却価格が残債を下回ると、売却後も残ったローンの支払いに悩まされることになります。特に、住宅市場が低迷している地域では、売却価格が予想よりも著しく下がることがあり得ます。その結果、計画が狂ってしまう事例も少なくありません。
また、買い手の住宅ローン利用も簡単ではないのです。よく住宅ローンの名義変更を期待されるご夫婦を見受けますが、ほぼ名義変更は認められないのです。また借入時の夫婦の状態も住宅ローン利用を制限しているのですが、理解不足からかご自身で金融機関へ融資相談し玉砕される方が後を絶たないという状況にもあります。
このような事態を避けるためには、早い段階で専門の不動産エージェントや法律家と相談し、どのようにローンの処理を行うか話し合うことが重要です。計画的に進めることで、離婚後の生活を見据えた適切な解決策が見出せるでしょう。
これらの事例からもわかるように、親族間での不動産売買は、しっかりとしたコミュニケーションと相手を思いやる姿勢が重要です。
まとめ
親族間売買における流れを理解することは、円滑な取引を実現するために非常に重要です。お互いに信頼する関係にある親族同士であっても、契約や手続きに関してはしっかりとしたルールを守る必要があります。
親族間の不動産売買には特有の流れがあり、しっかり理解しスケジュールを進めなければトラブルのもとにもなるので注意しましょう。まず、売主と買主は意思確認し、価格等を話し合います。売買契約書には物件の詳細、価格、引渡し日を明記する必要があり、これによってトラブルを防ぎます。手続きには登記関連書類の準備と専門家の助けが推奨されます。さらに感情的要素に配慮しつつ進行し、売買代金の支払い、登記手続き、税務申告も重要です。
コーラルは、親族間の不動産売買専門のスタッフ(親族間売買上級アドバイザー)が在籍し、適切な準備とコミュニケーションをもってスケジュール管理していますので、スムーズな取引を実現します。
この記事の執筆者、監修者
この記事の執筆者
井上朝陽 宅地建物取引士、住宅ローン設計士、親族間売買上級アドバイザー
専修大学卒業後コーラル株式会社へ。不動産売買業務従事10年以上の間、総計売買数700件以上を担当し成約する。コーラル大阪店開設にあたり店長として赴任、大阪圏の売買経験も積む。現在は本店に戻りコーラル勤務当初から大学で学んできたマーケテイングの知識を生かし、コーラルのWEBマーケティング統括責任者も務める。
住宅ローン設計士として不動産の親族間売買時の住宅ローンアドバイス実績はすでに300件以上熟し、金融機関からの信頼も厚い。
親族間で不動産取引するにあたり住宅ローン取り付けをどうしたらいいのかをYouTube動画で多数解説する活動も行う。
弁護士、司法書士、行政書士などの士業の立ち上げた親族間の問題を解決するための組織、一般社団法人結い円滑支援機構の立ち上げにも参画し現在は幹事も務める。
この記事の監修者
石井雄二 宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、親族間売買上級アドバイザー
不動産業界歴25年以上の間、さまざまな不動産関連の仕事に従事する中で宅地建物取引士兼ファイナンシャルプランナーとして1500名以上の方に住宅ローンのアドバイスを行う。コーラルではとても取得が難しいといわれる親族間売買上級アドバイザーとして月間10件以上、総計500名以上に住宅ローンアドバイスと取り付けを行う。金融知識、相続、住宅ローン問題等幅広い知識と業務経験を武器に、より多くのお客様の「人生にお役に立つ不動産運用の専門家を目指したい」との思いからコーラル株式会社に参画。
親族間で不動産取引するにあたり住宅ローン取り付けをどうしたらいいのかをYouTube動画で多数解説する活動も行う。
弁護士、司法書士、行政書士などの士業の立ち上げた親族間の問題を解決するための組織、一般社団法人結い円滑支援機構の立ち上げにも参画し現在は理事も務める。