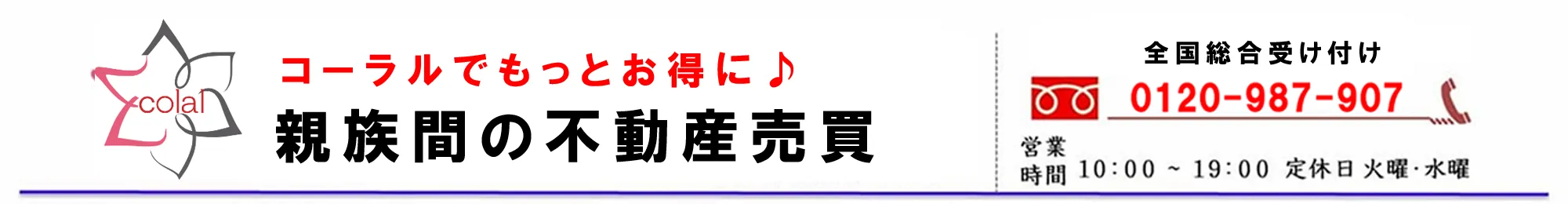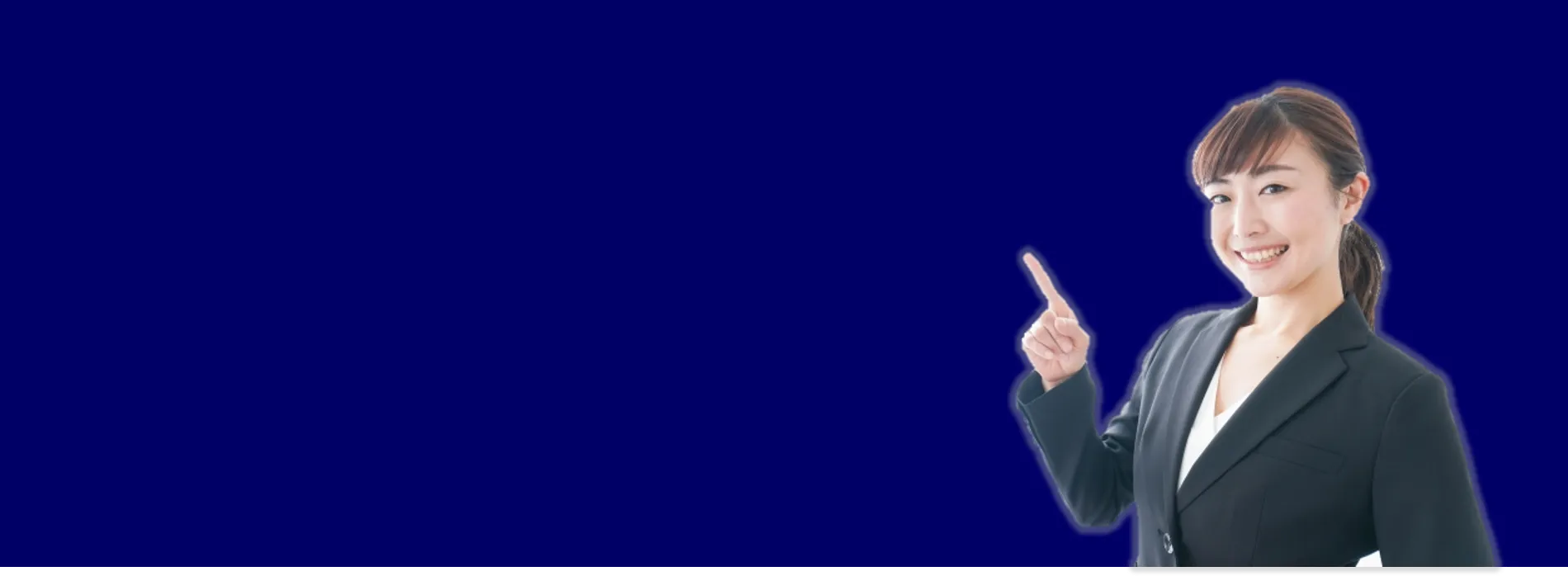親族間売買や親子間売買で住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、親族間売買とは、親子間(親子間売買)や兄弟姉妹間など直系血族や姻族との間での不動産の売買を指します。このような取引でも住宅ローン控除が適用される場合がありますが、一定の要件が存在します。
例えば、売買契約書の作成が必須です。この契約書には、購入価格や売主、買主の情報が記載されている必要があります。また、親族間売買での価格設定は公正であること(適正価格でみなし贈与にならないこと)が求められます。市場価格よりも著しく安い価格での売買は、税務上の問題を引き起こす可能性があります。
さらに、ローン契約は金融機関と住宅ローンとして取り交わす必要があります。不動産担保ローンや事業性融資などでは住宅ローン控除は利用できないのです。
また返済期間も重要になります。ゆえに金利や返済条件についても慎重に検討し、自身の家計と相談しながら進めることが大切です。これらの条件クリアで親族間売買でも住宅ローン控除の利用が可能となります。
親族間売買で住宅ローン控除を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。売買契約書の作成、公正な価格設定、自己居住用である等が求められます。また、住宅の床面積は50平方メートル以上(一部建物で40平方メートル)以上で、ローンの借入期間は10年以上である必要があります。確定申告が必要で、必要書類の準備も重要です。さらに、生計を共にしている親族との取引は控除対象外となります。これらの要件を理解し、適切に対処すれば、効果的に住宅ローン控除を活用できます。
ここでは、親族間売買における2025年5月時点での住宅ローン控除の要件や、制度利用のポイントについて、親族間売買で住宅ローン取り扱いを500件超こなしている親族間売買上級アドバイザー兼宅地建物取引士の井上朝陽が解説します。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームの新築・取得・増改築などを行った場合に、一定の税額控除が受けられる制度です。
これにより、年末時点で残高がある住宅ローンに基づいて、所得税の一部(一部、翌年の住民税)が軽減されます。特に新築や中古住宅を購入する際に、返済負担を軽減する手段の一つとして多くの人に利用されています。
具体的には、住宅ローンの借入額に応じて、年末時点の残高に基づいて所得税が一定割合減少します。控除の対象となるのは、 融資を受けた住宅の居住用部分に限られ、投資用や別荘などの用途には適用されません。また、控除を受けるためには、一定の条件を満たすことが求められます。
さらに、この控除制度には、利用期間が設けられており、初年度から最大10年間の控除を受けられるケースが一般的です。しかし、具体的な条件や金額は制度の改訂により変わる場合があるため、最新の情報の確認は重要です。特に親族間売買を検討している方は、必要な書類や手続きについても事前に理解を深めることが必要です。
住宅ローン控除の概要
住宅ローン控除の概要について説明します。住宅ローン控除は、住宅を購入するために借りたローンの利息に対して、所得税から一定額を控除できる制度です。この制度は、家計の負担を軽減する目的があり、多くの家庭に利用されています。
具体的には、住宅ローンの年末残高に基づいて、控除額が算出されます。一般的に、控除は借入額の一定割合で計算され、最大で10年間にわたって適用されるケースが多いです。初年度には控除額が大きく、年々減少していくのが一般的な仕組みです。
ただし、住宅ローン控除の適用を受けるためには、親族間売買に限らず一般的な不動産取引でも一定の条件があります。
例えば、購入する住宅が居住用である事や、契約が正式に成立している事、または必要な書類を用意する事が求められます。特に親族間売買の場合、市場価格に見合った取引であることが重要です。
さらに、利用申請には確定申告が必要ですので、忘れずに手続きする必要があります。これらの条件をしっかりと理解し、準備を進めることで、住宅ローン控除は有効に活用できるでしょう。この制度は、住宅購入時の資金繰りにおいて大きな助けとなります。
住宅ローン控除の控除額
住宅ローン控除の控除額は、借入れた住宅ローンの残高に基づいて算定されます。
具体的には、年末時点での住宅ローン残高に一定の控除率を掛けた額が、その年の所得税から控除(一部、翌年の住民税)される仕組みです。一般的には、控除率は0.7%となっているケースが多いですが、条件によって異なることもあります。
例えば、年末時点での住宅ローン残高が3,000万円の場合、通常であれば21万円の控除を受けられる計算になります。これにより、自己負担の税金が減少し、経済的な負担軽減ができます。控除は最大10年間継続して受けれるため、長期的に見れば大きな金銭的メリットがあります。
ただし、控除額には上限が設けられています。特に新築住宅の場合は、購入価格や物件の種類によって異なる控除上限が適用されます。また、親族間売買の場合、特別な要件があるため、税務署や専門家との相談を通じて、正しい情報の確認が重要です。
このように、住宅ローン控除は、計画的な返済を促し、住宅購入を支援する重要な制度ですので、ぜひ活用をお勧めします。
住宅ローン控除を受けるための手続き
住宅ローン控除を受けるための手続きは、いくつかのステップに分かれています。
まず最初に、住宅を購入したら、確定申告を行う必要があります。これにより、所得税控除の申請ができます。通常、購入した年の翌年に行うことが一般的ですが、正確な日程は税務署のサイトでの確認をおすすめします。
次に、確定申告の際には、必要書類の準備が重要です。
具体的には、住宅ローンの残高証明書、売買契約書、住民票の写し、そして所得を証明する書類などが必要です。これらの書類は、住宅ローン控除を受けるために必要不可欠ですので、失くさないようにしておきましょう。
さらに、親族間売買の場合には、特別な注意が必要です。通常の売買と異なり、市場価格との整合性が求められます(適正価格の設定)ので、公正な親族間取引であることを証明する書類が必要となるケースがあります。
最後に、手続きは正確に行うことが非常に重要です。また、税務署からの指摘や質問に対して、スムーズに対応できるように準備しておくと良いでしょう。これらの注意点を押さえれば、スムーズに住宅ローン控除を受けることができるはずです。
住宅ローン控除を受けるための要件
住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの重要な要件があります。
まず第一に、住宅を取得するために借入を行い、その貸付金に対して実際に返済を行っていることが求められます。借入金が住宅の取得や建築の目的であることが必要です。
次に、対象となる住宅は、自己居住用であると明確でなければなりません。親族間売買で取得した住宅が、居住するための物件であると証明する必要があります。また、その住宅が適用対象となる耐震基準や設備基準など、一定の基準を満たす事も要件の一つです。
さらに、売買契約書を作成し、適切に手続きが行われていることも重要です。契約書には、売買価格や物件の情報、購入日などが正確に記載されている必要があります。
最後に、控除を受けるためには、申告を行うことが不可欠です。
確定申告で必要な書類を整え、期限内の提出が求められます。これらの要件をしっかりと把握し、準備を整えておけば、住宅ローン控除をスムーズに受けることが可能になります。
下記では住宅ローン減税の基本的な概要について国土交通省HPにある図が分かりやすいので貼り付けいておきます。

建物に関する要件
住宅ローン控除を受けるためには、建物に関する要件がいくつかあります。
まず、住宅として利用される建物が、自己の居住のために取得される必要があります。これは、親族間売買であっても同様です。つまり、購入した住宅にしっかりと住むことが求められます。居住用であると証明されない場合、住宅ローン控除の対象外となる場合があります。
次に、対象となる建物は、法令で定められる一定の基準を満たす必要があります。具体的には、耐震基準のクリアが求められます。これは、地震による安全性を確保するための要件であり、購入する物件が適合しているかの確認が不可欠です。
さらに、住宅の取得時期も重要です。2022年の10月以降に新築または購入した物件でない場合、適用を受けられないことがあります。また、リフォーム等で住宅を改修した場合も、一定の条件を満たさない限り控除対象外となるため注意が必要です。
これらの要件をしっかりと把握し、自身の住宅が条件を満たすかどうかを確認することで、スムーズに住宅ローン控除を受けることができるようになります。親族間売買であっても、正しい手続きと要件の確認を怠らずに行うことが大切です。
控除の適用対象となる住宅ローンの上限は、以下のいずれかに該当する場合は3,000万円、それ以外は2,000万円になります。
【借入限度額が3,000万円になる住宅】
〇 長期優良住宅
〇 低炭素住宅
〇 ZEH水準省エネ住宅
〇 省エネ基準適合住宅
通常、親族間売買で売主と買主が住宅を取引するときは中古住宅(既存住宅)になるでしょう。中古住宅を取得した場合は、共通条件に加えて下記の条件を満たせば住宅ローン控除の適用を受けられます。
建築後使用されたことのある家屋で、次のいずれかに該当すること
- 1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたもの
- 業者が耐震改修工事をしたか居住までに耐震基準を満たすことが証明されたもの
ただし、中古住宅については、新築物件や買取再販住宅に比べて、借入限度額や控除期間が異なっているため注意が必要です。
- 借入限度額:最大3,000万円
- 控除期間:10年間
※省エネ基準に適合しない住宅(「その他の住宅」)の場合は次のいずれかの書類が必要となります。
[1]2023年12月31日以前に建築確認を受けたことを証する確認済証又は検査済証の写し
[2]2024年6月30日以前に建築されたことを証する登記事項証明書
※この場合、適用される借入限度額は2,000万円、控除期間は10年となりますので、ご注意ください。
※2024・2025年に「その他の住宅」に入居する場合で[1][2]いずれも証明できない場合、住宅ローン減税の対象外となります。
※床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は、[1]の提出が必須となります。
売り主と買い主の関係性に関する要件・生計を共にしている場合は適用外
親族間売買で住宅ローン控除を適用する際の特別な留意点の一つに、「生計を共にしている場合は適用外」という規定があります。この点について詳しく理解しておきましょう。
生計を共にしているとは、同じ住居で生活を共にしている家族や親族のことをいいます。
一般的に、親や子どもなどの直系親族が一つの家計を持っている場合、住宅ローン控除の対象に該当しない場合が多いです。また仕送りをしている場合も適用外になります。たとえ別居していても、生活費の仕送りがある場合などは「同一生計」とみなされるのです。
つまり、親族間売買であっても、ますます密接な関係を持つ者同士の取引では、控除は受けれません。
この規定は、税務上の公平性を保つためのものであり、同じ家計の中での取引は、実質的に自己取引と見なされ、税金の優遇措置を利用する目的には合致しないとされています。したがって、親族から住宅を購入する場合は、その親族と生計を別にし、独立した経済活動が行える状況を整える必要があります。
この条件を考慮せずに親族間売買を進めてしまうと、後々の税制面でのトラブルを引き起こす可能性がありますので、細心の注意を払うことをお勧めします。特に、親族との関係性や生活状況を見直しながら、住宅ローン控除を有効に利用できる方法を模索することが重要です。
買い主の居住用の家であること
住宅ローン控除を受けるための条件の一つに、買い主の居住用の家であることが挙げられます。
つまり、親族間売買によって取得した住宅は、本人が実際に居住するためのものでなければなりません。
これにより、単なる投資物件や賃貸用の不動産には住宅ローン控除が適用されないことがあります。
この要件の重要なポイントは、購入した住宅が「自己居住用」であると証明する必要があるということです。具体的には、住民票や電気・水道などの公共料金の請求書を通じて、実際に居住している事を示す必要があります。この証明は、税務署からの確認が行われる場合もあるため、しっかりと準備しておきたいものです。
さらに、親族間売買の場合、居住用であることを理解していない場合もあるかもしれません。例えば、親から子へ家を譲る際に、子どもが他の場所に住んでいる場合は、居住用としては認められないケースがあります。したがって、居住の意志を明確にしておくことが重要です。
このように、住宅ローン控除を利用するためには、買い主が実際に居住する家であるとの証明が不可欠です。しっかりと条件を確認し、居住用の要件を満たすよう準備をすることが、控除を受けるための第一歩となります。
住宅の広さや面積に関する要件
住宅ローン控除を受けるためには、住宅の広さや面積に関する要件も考慮する必要があります。
具体的には、住宅の床面積が一定の基準を満たしていることが求められます。一般的には、自己居住用の住宅として利用する場合、床面積が50平方メートル以上であることが要件とされています。
店舗併用住宅の場合は、面積の二分の一以上が居住エリアであることも条件となります。
また、親族間売買で取得した住宅も同様に基準を満たす必要があります。仮に、床面積が50平方メートル未満である場合、住宅ローン控除は受けれません。さらに、一戸建てやマンションなど、住宅の種類によっても条件が異なるケースがありますので、十分なる確認が重要なのです。
なお、親族間売買の場合には、税務署からのチェックが厳しくなる場合があります。適切な申告を行うためには、売買契約時に必要な面積の証明書や図面をしっかりと整備しておくことが必要です。
このように、住宅の広さや面積については、住宅ローン控除を受けるために必ず確認し、適切な手続きを行うことが重要です。要件を満たすことで、税負担を軽減し、より快適な住環境を手に入れることが可能になります。
ローンの借入期間の要件
住宅ローン控除を受けるためには、ローンの借入期間にも特定の要件があります。
まず、基本的な条件として、住宅ローンの借入期間が10年以上であることが求められます。返済期間が10年に満たない場合は、適用対象外となりますので、ローン契約を締結する際には十分に確認しておくことが大切です。
また、親族間売買の場合でも、同様に10年以上の借入が必要です。そのため、金融機関としっかりと話し合い、自分に合った返済プランを立てることが求められます。借入期間が短い場合、たとえ条件を満たしていても、住宅ローン控除が適用されない場合があります。
さらに、借入期間中にもし返済を滞納してしまうと、控除を受ける資格を失う可能性があるため、十分な返済計画を立てる事が必要です。家計に無理がないよう、適切な額の借入をおすすめします。
以上の要件を理解した適切な対応で、親族間売買であっても住宅ローン控除を受けることができ、将来の負担を軽減する手助けとなります。事前の準備と話し合いが重要です。
入居要件
原則として、取得から6か月以内に買主が居住を開始し、住宅ローン控除を受ける各年の年末(12月31日)まで居住していることが条件となります。
しかし、家屋の所有者が、転勤等のやむを得ない事情により、その住宅の取得等の日から6か月以内にその者の居住の用に供することができない場合や年末まで引き続き居住することができない場合もあります。このような場合であっても、一定の要件を満たす場合に限り、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができます。
詳細は国税庁HPでご確認ください。⇒ 国税庁HP【転勤と住宅借入金等特別控除等】
他の制度との併用の制限
他の制度との併用には、親族間売買の場合でもいくつかの制限が存在します。
例えば、住宅ローン控除を利用する場合、同時に他の住宅取得支援制度の利用が難しいケースがあります。特に、同じ年度内に複数の制度から助成を受けることができない場合があり、どの制度を選択するか慎重に判断する必要があります。
具体的な例としては、以下の二つの制度を利用した場合は住宅ローン控除を利用できません。
〇 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
〇 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができますが、住宅借入金等特別控除は併用できません。
また、住宅取得等資金贈与の特例を利用して資金を受け取った場合、住宅ローン控除は併用可能ですが、適用範囲に制限が生じます。そのため親族間売買の際は、これらの制度についても理解しておくことが重要です。
住宅ローンの借入れ先や契約条件によっても、併用の可否が変わることがあります。金融機関によっては、特定の補助金や制度との併用を認めないところもあるため、事前に確認を取ることが必要です。
併用を検討する場合は、各制度の詳細をよく理解した上で、必要な手続きを行うことが大切です。長期的な視野で自分にとって最適な選択をするためにも、専門家の意見を参考にしつつ、慎重に進めていくことをお勧めいたします。
まとめ
親族間売買や親子間売買においても、住宅ローン控除は可能ですが、いくつかの利用の条件を理解しておく必要があります。まず、親族間での売買契約は必ず書面で行い、内容を明確にすることが重要です。これにより、後々のトラブルを防ぎつつ、税務上の問題回避ができます。
さらに、購入価格が市場価値から逸脱している場合、税務署から疑義を持たれる可能性があるため、公正な価格での契約が求められます。親族間でも、過度に安い価格設定は避けるようにしましょう。
金融機関との金銭消費貸借契約(住宅ローン契約)も忘れずに行う必要がありますす。親族間売買の場合でも、銀行や信用金庫から住宅ローンを組むことができます。その際の金利や返済条件について、慎重に計画を立てることが成功の鍵となります。以上の条件遵守で安心して住宅ローン控除を受けることができるでしょう。
この記事の執筆者、監修者
この記事の執筆者
井上朝陽 宅地建物取引士、住宅ローン設計士、親族間売買上級アドバイザー
専修大学卒業後コーラル株式会社へ。不動産売買業務従事10年以上の間、総計売買数700件以上を担当し成約する。コーラル大阪店開設にあたり店長として赴任、大阪圏の売買経験も積む。現在は本店に戻りコーラル勤務当初から大学で学んできたマーケテイングの知識を生かし、コーラルのWEBマーケティング統括責任者も務める。
住宅ローン設計士として不動産の親族間売買時の住宅ローンアドバイス実績はすでに300件以上熟し、金融機関からの信頼も厚い。
親族間で不動産取引するにあたり住宅ローン取り付けをどうしたらいいのかをYouTube動画で多数解説する活動も行う。
弁護士、司法書士、行政書士などの士業の立ち上げた親族間の問題を解決するための組織、一般社団法人結い円滑支援機構の立ち上げにも参画し現在は幹事も務める。
この記事の監修者
石井雄二 宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、親族間売買上級アドバイザー
不動産業界歴25年以上の間、さまざまな不動産関連の仕事に従事する中で宅地建物取引士兼ファイナンシャルプランナーとして1500名以上の方に住宅ローンのアドバイスを行う。コーラルではとても取得が難しいといわれる親族間売買上級アドバイザーとして月間10件以上、総計500名以上に住宅ローンアドバイスと取り付けを行う。金融知識、相続、住宅ローン問題等幅広い知識と業務経験を武器に、より多くのお客様の「人生にお役に立つ不動産運用の専門家を目指したい」との思いからコーラル株式会社に参画。
親族間で不動産取引するにあたり住宅ローン取り付けをどうしたらいいのかをYouTube動画で多数解説する活動も行う。
弁護士、司法書士、行政書士などの士業の立ち上げた親族間の問題を解決するための組織、一般社団法人結い円滑支援機構の立ち上げにも参画し現在は理事も務める。